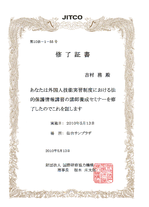FAQ
障害年金を受給するためには?
- 国民年金(障害基礎年金)の場合
次の3つの要件が満たされないと受給できません。- 初診日要件
次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。- 国民年金の被保険者であること
- 国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所が有り、かつ、60歳以上65歳未満であること
- 保険料納付要件
- 原則:
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること - 特例:
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、平成28年3月31日までに初診日があり,その初診日時点において65歳未満である場合に限ります。
- 原則:
- 障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又はそれまでに障害が固定した日)において、障害等級1級又は2級の障害状態にあること。
- 初診日要件
- 厚生年金保険(障害厚生年金)
次の3つの要件を満たさないと受給できません。- 初診日要件
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること
例えば、初診日がサラリーマン(厚生年金)のときにあれば、その後自営業等で国民年金に入っていたとしても、他の要件が満たされれば、障害厚生年金を受給することができます。
体調が悪く会社を辞めるときは、必ず受診してから、退職をすることをお薦め致します。 - 保険料納付要件
- 原則:
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間で満たされていること - 特例:
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、平成28年3月31日までに初診日があり,その初診日時点において65歳未満である場合に限ります。
- 原則:
- 障害認定日要件
障害認定日(初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日又はそれまでに障害が固定した日)において、障害等級1級、2級又は3級の障害状態にあること。
- 初診日要件
初診日とは?
今回の障害の原因となった疾病又は負傷について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです。
従って、複数の病院で治療を受けている場合、初診日は今回の疾病又は負傷について最初に受診した病院で、医師に初めて診察を受けた日になります。
例①:
- 発病
- A病院受診
- B病院へ転医
- C病院で受診中
の場合、A病院での最初の受診日が初診日になります。
例②
会社の定期健康診断等で異常が指摘され、その健康診断を実施した医療機関の医師から、治療に関する指示や他の医療機関で精密検査を受けるように指示が出た場合は、当該健康診断日が初診日になります。
初診日は重要!
- 初診日に加入している年金制度によって、受給する障害年金が決まります。
- 保険料納付要件を判定する、基準日になります。
従って、初診日が決まらないと保険料納付要件を満たしているかどうか判定できません。 - 障害認定日は、初診日から起算されます。
従って、初診日が決まらないと障害認定日も決まらなく、障害状態の評価もできなくなるので、障害認定もできないということになります。
※尚、初診日は、正式に医師から診断名の通知を受けた日であると、誤解されている方が良くありますが、前記しましたように、そうではありませんのでご注意下さい。
又、診断名が異なっても医学的な観点から相当因果関係が認められれば、最初の疾病又は負傷に係わる初診日が、その初診日になりますのご留意下さい。
初診日証明が取得できないが・・・
- カルテの保存期間は原則5年です。が、すべての病院が原則通り廃棄処分しているとは限らないこともありますので、初診時の病院に良く確認して見て下さい。
- カルテが保存されていない場合、当時の受診受付簿や入院記録から初診日証明である、「受診状況等証明書」が作成できれば問題ないです。
- 受診受付簿や入院記録もない場合は、次の資料等があれば、初診日証明に代えて参考資料として提出できるケースがあります。
- 労災の事故証明
- 交通事故証明
- 健康保険の療養給付記録
- 身体障害者手帳の交付時の診断書
- 勤務先の定期健康診断の記録
心臓ペースメーカーを装着した場合の障害認定日は?
医師の所見等から症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至ったと判断された場合、原則である初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日より前であっても、障害年金が支給される場合があります。
具体例:
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
- 人工骨頭、または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、または人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門、または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設、または手術を施した日
- 切断、または離断による肢体の障害は、原則、切断、または離断した日
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
20歳前に障害者になったときは?
保険料納付要件が問われません。
従って、障害認定日に障害等級に該当する障害状態にあれば、国民年金から障害基礎年金が受給できます。
次の3ケースが考えられます。
- 初診日・障害認定日共に20歳前にあるケース
障害認定日において障害等級に該当する障害状態にあれば、20歳に達した日に障害基礎年金の受給権が発生致します。 - 初診日が20歳前で、障害認定日が20歳後のケース
障害認定日において障害等級に該当する障害状態にあれば、障害認定日に障害基礎年金の受給権が発生致します。 - 初診日が20歳前で、障害認定日又は20歳に達した日のうち、いずれか遅い方の日において障害等級に該当していないケース
65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する障害状態にあれば、その請求日に障害基礎年金の受給権が発生致します。
※20歳前障害においては、初診日証明を取得することが難しい状況になることが多いですので、初診日証明(受診状況等証明書)を早めにとることが望まれます。特に有効期限がありませんので。
特に幼少期に初診日がある場合、20歳を過ぎての初診日証明を取得するのに困難を伴います。
20歳前の障害年金の所得制限とは?
本人に一定以上の所得がある場合、政令で定められる額を超えたとき、障害年金の全部又は一部が支給停止となります。
- 本人の前年度の所得が462.1万円を超えた場合は、
年金が全額支給停止となります - 本人の前年度の所得が360.4万円を超えた場合、
年金額が半額支給となります。
※「政令で定められる額」とは
①根拠法令‥‥国民年金法施行令第5条の4第1項、同第2項
扶養親族が0人のとき‥‥360万4千円
扶養親族があるとき‥‥360万4千円に、扶養親族1人につき
38万円を加算した額
②扶養親族に関する加算(当該扶養親族1人につき)
通常の扶養親族‥‥38万円
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族‥‥48万円
特定扶養親族‥‥63万円
③2分の1支給停止
①と②により計算した額が
「360万4千円 + 38万円×扶養親族数」超えたとき
④全額支給停止
①と②により計算した額が
「462万1千円 + 38万円×扶養親族数」を超えたとき
※所得が一定以上の場合、年金が支給停止になり、制限を受けますが、受給権がなくなるわけではありません。将来、所得が限度額以下になった場合、再支給されます。
事後重症とは?
障害認定日に障害等級に該当する障害状態になく、その後、病状が悪化して所定の障害等級に該当する障害状態になった場合、65歳に達する日の前日までに請求することによって障害年金を受給できる制度です。
事後重症の場合請求によって初めて受給権が発生し、その請求日の属する月の翌月から障害年金の支給開始となります。
従って、できるだけ早く請求手続を済ませることが肝要となります。(過去には一切遡及はしません)
又、請求日の期限は65歳に達する日の前日までですので、請求日については、充分な注意が必要となります。
障害年金の請求に時効はあるのでしょうか?
障害年金(国民年金・厚生年金共に)の時効は、5年となっています。
実際の運用では、障害認定日(受給権発生日)から5年以上経過した場合でも遡及請求が認められています。
尚、年金の支払いについては、障害認定日まで無制限に遡及できるのではなく、請求日から最大限5年間分を遡及することになります。
ただし、このように遡及できるのは、障害認定日請求が認められる場合に限られます。
ここでの課題は、5年以上経過した障害認定日時点の診断書が取得できるのか、また、それより1年6ヶ月遡った初診日証明が取得できるのか、ということになります。
もし、それらが取得ができない場合は、事後重症扱いになり、遡及支払は行われません。
ポイント:病院で診察を受けた記録は、必ず残すことが重要になります。